
完全分離型二世帯住宅の間取りのポイントとは?後悔や失敗を防ぐコツ
住まいづくり
高齢化や共働きの家族が増えている近年、親世帯と子世帯の同居が注目されています。そんな中、《世帯ごとに間取りを完全に分離するタイプの二世帯住宅》に関心が集まっているようです。
とは言え、完全分離型の二世帯住宅にはデメリットもあるため、情報収集が欠かせません。長所と短所の両方を理解しておくことで、あとで後悔するリスクが下がり、満足度が高まるでしょう。
本稿では《完全分離型二世帯住宅の間取りのポイント》や、後悔や失敗を防ぐために知っておきたい情報をお届けします。親子の同居をご検討中の方は、ぜひ最後までご覧ください。
完全分離型二世帯住宅とは?間取りの特徴や人気の理由

まずは、完全分離型の二世帯住宅の特徴や、人気の理由をご紹介します。あなたのご家族に適していそうか、判断するためのヒントにしてください。
間取りの特徴
二世帯住宅とは《ふたつの世帯が一緒に暮らすために設計された住宅》のことです。一般的には《親世帯と子世帯が同居するための家》を指すことが多いでしょう。
二世帯住宅を大別すると、以下の3つのタイプに分けられます。
- 完全共有型:寝室以外のほぼすべての空間を共有
- 一部共有型:玄関や浴室など、一部の空間を共有
- 完全分離型:世帯ごとに居住空間を分離
本稿でご紹介する完全分離型の二世帯住宅は、各世帯の居住空間を以下のどちらかの方法で分けるのが一般的です。
| 上下で分離 | 子世帯が上階、親世帯が下階に住むケースが多い。ワンフロアで生活できる。 |
|---|---|
| 左右で分離 | 上下で分けるより、騒音問題が起きにくい。どちらの世帯も階段の上り下りが発生する。 |
完全分離型の二世帯住宅では、電気やガス、水道も分けるケースが少なくありません。各世帯の使用量を個別に計測できるように、メーターを別々に設置します。
人気の理由
2024年4月に、既婚男女499人を対象に「二世帯住宅の間取りに関する意識調査」が実施されています。
この調査の結果によると「二世帯住宅にするなら間取りはどうするか」という質問に対し、「完全分離型」を選んだ人が79.8%(398人)に達したそうです。
現代社会では、高齢化や共働き世帯の増加、そして個人の価値観の多様化が進んでいます。
その結果、親世帯も子世帯も「同居までは望まないが、近居なら何かと助け合えてよい」と考える傾向が強まり、上述のような圧倒的な結果になったのではないでしょうか?
たとえば、回答者は以下のような複雑な心境なのではないかと推察されます。
- 各世帯の独立性を保ちたい
- プライバシーを確保したい
- 同居によるストレスを避けたい
- 適度な関わりを維持したい
- 必要なときはサポートし合いたい
完全分離型の二世帯住宅は、これらのニーズを満たせます。それぞれの世帯が自分たちのライフスタイルに合わせて生活でき、困ったときはすぐに助け合えるでしょう。
時代に合った選択肢として、完全分離型二世帯住宅の人気が高まっていると考えられます。
完全分離型二世帯住宅の間取りの注意点(デメリット)
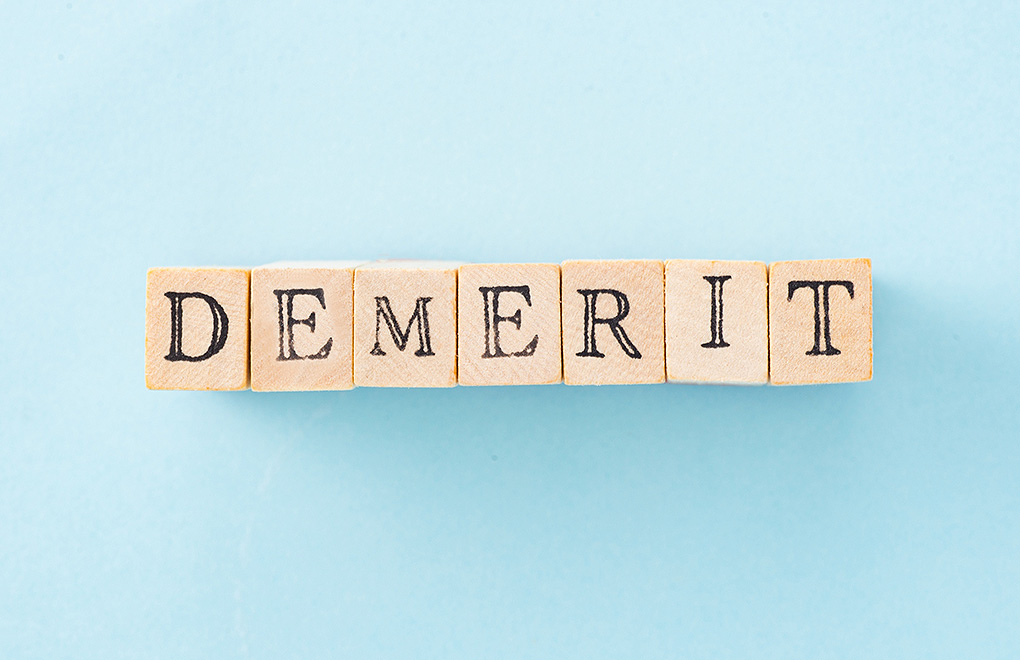
しかし、冒頭でご紹介したとおり、完全分離型二世帯住宅の間取りにはデメリットもあります。ちゃんと短所も理解しておかないと、「こんなはずじゃなかった」と後悔することになりかねません。
ここでは、とくに注意したいデメリットを3つご紹介します。
- 2世帯分の間取りが必要になるため、建築費用が高額になる
- 各世帯が独立しているため、水道光熱費が2世帯分かかる
- 一般的な住宅と比べて、売却しにくい側面がある
順番に、詳しく解説していきましょう。
2世帯分の間取りが必要になるため、建築費用が高額になる
完全分離型は、他のタイプの二世帯住宅と比較すると、建築費用が高額になる傾向があります。なぜなら、2世帯分の独立した生活空間を確保する必要があるからです。
たとえば、以下のような間取りが2世帯分必要になります。
- 玄関
- 浴室
- トイレ
- リビング・ダイニング・キッチン
- 寝室(私室)
- 収納スペース
これらの設備や空間を2世帯分設けるということは、当然ながら、材料費や人件費などの建築コストの増加につながります。
あわせて、必要な間取りが収まるように、広い土地も必要になります。ですから、いざ建てるとなると、コスト面での負担が大きくなりがちです。
実際、あるアンケート調査(2019年)で2年以内に二世帯住宅を建てた方に「二世帯住宅のタイプを教えてください」と質問したところ、以下の結果になったそうです。
- 完全共有型:31.3%
- 一部共有型:43.4%
- 完全分離型:25.3%
一部共有型を採用した理由では「建築費用が抑えられる (40.0%)」がトップだったようです。コストアップしがちな「完全分離型」は3位でした。
ふたつのアンケート調査の結果から「できれば間取りを分離したいが、コストを考えると一部共有もやむなし」という現実が垣間見えます。
完全分離型二世帯住宅を実現するには、コスト管理が必要です。建物でコストダウンを図るのが難しい場合は、購入する土地でコストダウンを図る等のバランス感覚が必要でしょう。
各世帯が独立しているため、水道光熱費が2世帯分かかる
完全分離型二世帯住宅では、光熱費が2世帯分発生します。各世帯が独立した生活空間を持ち、それぞれに電気・ガス・水道などの設備を備えているため、使用量や基本料金が2世帯分になるからです。
とりわけ近年では、電気代が高いですよね。家庭の電力消費量は「エアコン、冷蔵庫、照明」で5割以上を占めます。このような家電を共有しないため、完全分離型は電力消費が非効率になります。
では、完全分離型二世帯住宅の光熱費を削減するには、どうすればいいのでしょうか?—— 対策としては、以下が有効です。
- 省エネ性能の高い住宅を建築
- 高効率のエアコンや冷蔵庫の購入
- LED電球の利用
- 太陽光発電システムの導入
上述のような対策を講じることで、効率的に電気代を削減できます。完全分離型の二世帯住宅をご検討中の方は、ぜひ覚えておきましょう。
一般的な住宅と比べて、売却しにくい側面がある
完全分離型の二世帯住宅は、一般的な住宅と比べて、売却しにくい側面があります。なぜなら、需要が限定されるため、買い手を見つけにくいからです。
では、二世帯住宅を売却したくなるのは、どんなときでしょうか?恐らく、親御さまが亡くなられ、1世帯分の居住スペースを持て余すようになったときではないでしょうか?
それならば、将来的に1世帯分を賃貸に出すことも見据え、以下のような設計にしておくとよいでしょう。
- 防音対策を厳重にする
- 共有スペースをつくらない(玄関アプローチやお庭も含む)
- 水道・ガス・電気は別々にメーターを設置しておく
二世帯住宅は売却しにくい側面があるため、将来の家族構成や活用方法まで考慮して設計することが大切です。ひとつの対処法として賃貸も検討しておくと、選択肢が広がります。
賃貸に出せる二世帯住宅は、賃貸住宅として活用できるだけでなく、不動産投資家に買ってもらえる可能性も高まります。
完全分離型二世帯住宅の間取りの魅力(メリット)

つづいて、完全分離型二世帯住宅のメリットをご紹介します。
- 各世帯が、それぞれのニーズに合わせて間取りを設計できる
- プライバシーを確保しやすく、生活リズムの違いを気にせず生活できる
- 親世帯から子世帯へ相続が発生したあと、空いたほうを賃貸に出せる
それぞれ、詳しく解説していきましょう。
各世帯が、それぞれのニーズに合わせて間取りを設計できる
世帯ごとに完全に独立した空間を実現できる「完全分離型二世帯住宅」の間取りは、各世帯がそれぞれのニーズに合わせて設計できます。
部屋数や広さ、内装や設備なども、各世帯の家族構成やライフスタイルに合わせて自由に決められます。たとえば、親世帯の居住スペースのみ重点的にバリアフリー設計にすることも可能です。
ただし、ご予算や土地面積による制約も考慮する必要があります。場合によっては、間取りや設備のグレードを調整しなければならないこともあります。
そのため、ご予算を考慮しながら、できるだけ広い土地を用意することが重要となります。計画段階で両世帯がじゅうぶんに話し合い、優先順位をつけながら希望を擦り合わせていくことも大切です。
プライバシーを確保しやすく、生活リズムの違いを気にせず生活できる
完全分離型二世帯住宅は、プライバシーを確保しやすいでしょう。生活リズムの違いを気にせず暮らせるという点が、近年人気が高まっている理由のひとつになっています。
たとえば、親世帯と子世帯で起床時間や就寝時間が大きく違う場合、お互いに気兼ねしながら生活しなければなりません。一方、完全分離型の二世帯住宅ならその必要がなくなります。
食事の時間や入浴の時間なども、それぞれの世帯の都合に合わせて自由に決められます。完全に独立した生活空間があることで、各世帯がストレスなく自分たちのペースで暮らせるのです。
ただし、完全分離型は、完全共有型や一部共有型に比べて世帯間のコミュニケーションが減少しがちです。ときどき夕食を共にするなど、工夫が必要になります。
親世帯から子世帯へ相続が発生したあと、空いたほうを賃貸に出せる
完全分離型二世帯住宅は、各世帯の生活空間が玄関から完全に分離されています。ですから、他人に貸し出しやすいでしょう。
たとえば、親御さまがお亡くなりになったあと、空いたほうを利用して賃貸経営ができます。賃貸に出すことで家賃収入が得られれば、住宅ローン返済や老後の生活資金の補填ができます。
ただし、賃貸に出す時点で住宅ローンが残っている場合は、事前に金融機関に相談して承認を得ておきましょう。勝手に進めると、あとで大変なことになる恐れがあります。
金融機関は《居住用》として住宅ローンを融資しているため、勝手に《事業用》に使うと契約違反になります。場合によっては、融資の全額返済を求められるでしょう。
完全分離型二世帯住宅を建てる際、後悔や失敗を防ぐコツ

最後に《後悔や失敗を防ぐために知っておいていただきたい情報》をお届けします。
登記の方法について、相続を考慮して、よく検討しよう
完全分離型二世帯住宅を建てる際には、登記の方法について、相続を考慮してよく検討する必要があります。
二世帯住宅の登記方法には、おもに以下の3つの方法があります。
| 単有登記 | 二世帯住宅を一戸の住宅として考え、親世帯または子世帯のどちらか一方の名義で登記。手続きが簡単で、登記費用が安く済む。資金を出した世帯が異なる場合、贈与税が発生する可能性があり。 |
|---|---|
| 共有登記 | 二世帯住宅を一戸の住宅として考え、親世帯と子世帯が共同名義で登記する方法。出資割合に応じて持分割合を決め、登記する。登記手続きが単独登記よりも複雑になる場合がある。 |
| 区分登記 | 二世帯住宅を二戸の住宅として考え、それぞれの世帯が独自の名義で登記する方法。完全分離型の住宅でのみ適用可能。不動産取得税や固定資産税の軽減措置を、親子それぞれが受けられる。 |
完全分離型の二世帯住宅は「区分登記」という方法で登記できます。この登記方法を採用すると、各世帯が不動産取得税や固定資産税の優遇措置を受けられるため、節税効果が高くなります。
一方《小規模宅地等の特例》と呼ばれる減税措置を利用できなくなるため、相続税の負担が大きくなる可能性があります。登記と税のことで悩んだときは、税理士等の専門家に相談しておくと安心です。
各世帯別々に居住スペースを持つため、広い土地を用意しよう
完全分離型二世帯住宅は、各世帯が独立した居住スペースを持つため、一般的な一戸建て住宅よりも広い土地が必要になることが多いでしょう。
プライバシー確保のために玄関の位置を離したり、それぞれの世帯に専用の庭やバルコニーを設けたりする場合には、さらに広い土地が必要です。では、どれくらいの土地が必要なのでしょうか?
推奨される延床面積の目安は、2人世帯なら23坪以上、4人世帯なら38坪以上です。計6人家族が暮らす60坪の家を建てるケースを想定して、容積率ごとに必要な敷地面積の目安を計算してみましょう。
ちなみに、容積率とは《敷地面積に対する、建物の延床面積の割合》のことで、建築基準法第52条により地域ごとに設定されています。容積率を超える規模の建物は、建築できません。
それでは、60坪の家を建てるのに必要な土地の広さを試算してみましょう。
- 容積率50%の場合:約120坪
- 容積率60%の場合:約100坪
- 容積率80%の場合:約75坪
- 容積率100%の場合:約60坪
- 容積率150%の場合:約40坪
- 容積率200%の場合:約30坪
いかがですか?容積率しだいですが、完全分離型の二世帯住宅を建てるなら、大きな土地が必要になりそうですね。完全分離型の二世帯住宅を建てるなら、広い土地のほうが有利なのです。
土地の資産価値が高い場合、大きな土地は固定資産税も高額になります。完全分離型の二世帯住宅を建てるなら、暮らしやすさを考慮しつつ、安くて広い土地を購入したいところです。
【まとめ】完全分離型二世帯住宅を建てるなら長所と短所を把握しよう
完全分離型二世帯住宅の間取りの特徴を、メリットとデメリットの観点から解説しました。ご紹介したとおり、長所と短所の両面がありますので、どちらも理解したうえで採用することが大切です。
また、意外と見落としがちなこととして、登記や土地の面積も注意が必要です。必要な間取りが入る大きさの土地をリーズナブルな価格で購入すれば、納税や資金計画がラクになりますよ。

東広島の分譲地「グリューネン入野」は、平均70坪超えで300万円台からご提供しています。広めの土地がリーズナブルに購入できるだけでなく、自然豊かで開放的な町並みも魅力です。
JR駅が徒歩圏内にあり、小学校も団地内にある好立地です。広めの土地にゆったりと二世帯住宅を建てたい方は、ぜひ見学にお立ち寄りください。








